2011年、国内も国外も激動、激震が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
ご無沙汰しておりました。また今年も徐々に更新してまいりますので、よろしくお願いいたします。
チュニジアから飛び火した民衆デモがリビアに到達し、「中東でもっとも強固な独裁体制」と言われていたリビアが動乱に揺れている。
カダフィ大佐は、「わたしは革命の指導者としてリビアに残る。最後の血の一滴まで戦い抜き、先祖の地で殉教者として命を全うする」と続け、「リビアはわたしの国だ」と叫んだ。
「最後の血の一滴まで戦う」、カダフィ大佐が徹底弾圧を宣言 写真3枚 国際ニュース : AFPBB News
カダフィ大佐は、あろうことか反体制デモを行う自国民に対し、軍隊をもって鎮圧、空爆を敢行するという暴挙に出た。
「革命の指導者として戦い抜く」って、一体何と戦っているつもりなのだろうか。彼が弾圧し、血を流して死んでいくのは革命を目指す殉教者たちなのではないだろうか。
ここはシータならずとも、「国が滅びて、王だけ生きてるなんて滑稽だわ」 とつぶやきたくもなるところだ。(c『天空の城ラピュタ』)
だがしかし、王ではないのだ。階級的にはたかが大佐である。40年も圧倒的権力を持って君臨統治する独裁者の階級が、なぜ大佐どまりなのだろうか。もっと元帥とか大将軍とかに昇格すればいいのに。
この謎をとく鍵はこの独裁政権の成り立ちにある。
1969年にリビアで起こったクーデターで、王家が追放され、カダフィ大佐を事実上の元首とする「共和国」が誕生したのだった。(その後国王も処刑されたりすることはなく、1988年、一家で英国に移住している。)
つまり、カダフィ大佐は、40年経った今でも、「王政を打倒した革命の指導者」としての自分でいるのだ。そして、自分を絶対権力者やブルジョワと一線を画す存在として置いておくために、あえて終身大佐を通しているということなのだろう。
カダフィ大佐は、旧世紀の悲しいロボット兵なのだ。
1969年の革命によって、エジプトのナセルに倣って儀礼的に大佐に昇格した。その後も、革命の初心を忘れないようにということで大佐の階級のまま現在にいたっている。在東京のリビア人民局(事実上の大使館)はこの説明を採っている[7]。
ムアンマル・アル=カッザーフィー – Wikipedia
さて、それにしても、「日本に生まれて良かった」と思わざるを得ない。
日本では、こういう悲劇が起こりようもないからだ。
それは、自然と闘い全てを奪い合ってきた歴史の「砂漠の民」と、自然と協和し助け合ってきた「小川の民」との、国民性の違いによるものだろう。
しかしそれ以上に、権力と権威が絶対的に分離していて、権威(皇室)が宗教的祭祀王として神聖化されているこの国家体制においては、こういう悲劇が起こりようもないのだ。
(櫻木)
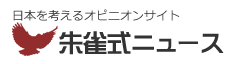
いつも拝見しています。ロストゼネレーションは私、S一桁も同様です。
滅びゆく日本・・・私の眼の黒い間にこれを見たくない、それまでに彼岸に行きたい、などと思っていたけれど、朱雀式さんを知って、なんと心強く感じたことか。日本はモラルハザードだと韓国のメディアが嬉しそうに書きたてているらしい昨今、今、日本のモラルの再びの構築はどうあればいいのか。明治のままの「教育勅語」でいいのか、それとも・・・考えがつきません。どうお考えですか、ご意見を聞かせてください。
ありがとうございます。そのように言っていただけるとこちらも心強く思います。
さて滅び行く日本をどう食い止められるか、どうすれば明治国家のように華麗に立て直せるか。
それはひとえに、我々まだ若い世代のこれからの努力いかんにかかっていると思います。
モラルの教育は、学校での教育勅語、地域社会での武士道、家庭でのしつけ、と三位一体となっていた時代が最も幸せだった時代でしょう。
あとは私たちが今後家庭を持ったときに、家庭内で教育勅語か、あるいはそれに類するものを制定し、小学校教育にも要望を出していくしかないでしょうね。
気になってました。→「カダフィ大佐は、なぜ大佐なのか」 http://t.co/VTldivM