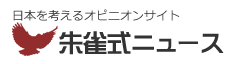いつの間にか三部作になってしまいました。「十二月八日を記憶せよ」シリーズ、今日で最後です。
前回は、1941年12月8日、大東亜戦争開戦の日を迎えた人々の声を紹介した。よく、したり顔で「民衆は軍部に騙されていた」「私は負けると知っていた」式のことを言う人がいるが、あんなものは戦後の後付けでしかない。開戦当初、日本中を、重い霧が払われたかのような喜びの空気が覆っていたのだ。今現在の我々でいうと、サッカーの日本代表が世界杯でベスト8まで進んだとして、その興奮を数倍したような感じではなかったかと想像する。
しかし、一般市民と違って、政府や軍部では、この戦争に明るい見通しが全く立たないことははっきり自覚していた。
時の首相、近衛文麿に日米戦争の見通しを聞かれた連合艦隊司令長官・山本五十六が「ぜひ戦争をやれといわれれば、初め半年や一年の間は、ずいぶん暴れてご覧にいれる。しかしながら、二年、三年となれば、まったく確信はもてぬ。」と答えたという逸話はあまりにも有名である。
また、山本五十六はドイツとの同盟にも否定的で、「日独伊三国同盟が出来たのは致し方ないが、こうなったら日米戦争を回避するよう、極力ご努力願いたい」とも要求したらしい。しかし当の近衛首相は、「負けると決まっている戦争に賛成するなど、祖先に申し訳が立たない」として内閣を総辞職してしまった。
開戦を回避しようとなんとか交渉を続ける日本に対してアメリカが突きつけた「ハル・ノート」は、日本が明治以降に手に入れた権益の全てを放棄し、ドイツ・イタリアとの同盟も破棄せよという強烈なもので、まさに「最後通牒」だった。ハル国務長官は「これで私の仕事は終わった。あとは海軍長官の仕事だ」と言ってのけた。つまり、ここまでやれば日本は開戦に踏み切らざるを得ない、あとは軍部でよろしく叩きのめしてくれたまえ、という意味である。
しかも、アメリカによって封鎖された日本の石油備蓄は2年分。そのままにしておけば、軍艦や飛行機を動かすことはできなくなる。あとは大阪城の濠を埋めた家康よろしく、アメリカはゆうゆうと上陸して日本とその全領土を好きにすることができる。いや、軍備どころか、石油がなくなれば国民生活も立ち行かなくなる。絶体絶命の苦境だった。
座して待つも死、立って戦うもまた死。
そのとき、駐米経験もある永野修身軍令部総長はこう決意した。
「戦うも亡国かも知れぬ。だが戦わずしての亡国は、魂までも喪失する永久の亡国である。たとえ一旦の亡国となるとも、最後の一兵まで戦い抜けば、我らの子孫はこの精神を受け継いで、再起するであろう。戦争が決定された場合、我ら軍人はただ大命の下で戦に赴き、最後まで戦うのみである。」
この言葉どおり、日本は最後まで戦い抜き、全アジアの独立の礎となるのと引き替えに国土は荒廃したが、戦後目覚しい復興を遂げた。しかし、今の日本はその魂を失っていないだろうか。アメリカに国土はおろか精神まで支配され、東亜の平和も日本人の誇りも忘れ、亡国への道に差しかかってはいないだろうか。戦後60年。
日本は果たして、経済的繁栄以外のものを取り戻せただろうか。
(櫻木)